
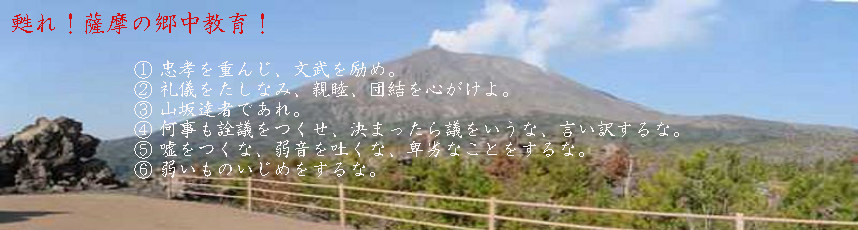
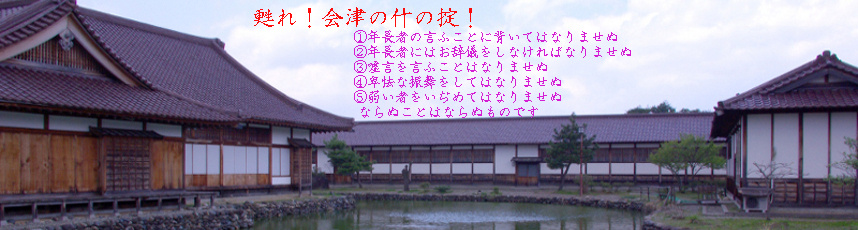
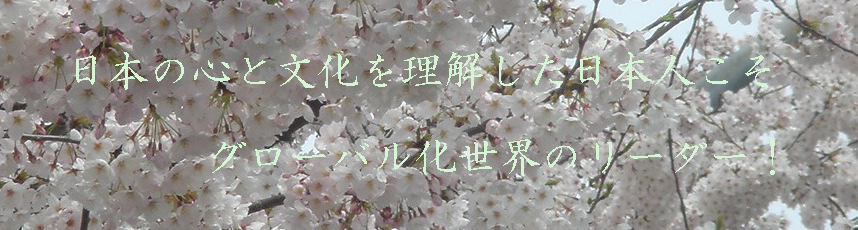
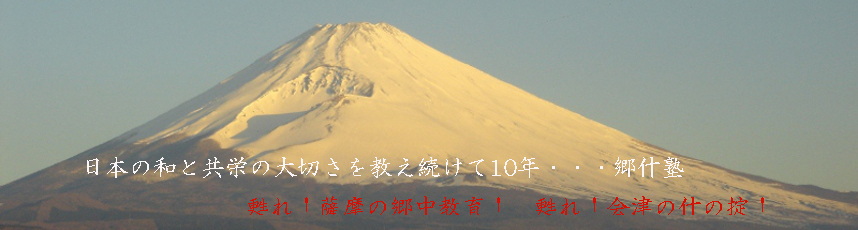
- 講演実績(演題)
- 世界最強!海上自衛隊護衛艦のチーム力
- 米海軍をも凌駕する海上自衛隊護衛艦のチーム力/日本海軍の伝統精神、和と共栄
- 人を動かすリーダーの条件
- 真のリーダーシップとフォロワーシップ
- 海上部隊指揮官(艦長)の絶対感性から見える経営者に必要な絶対感性
- 海自作戦要務による作戦計画作成手法/ロジカルシンキングによる命令・指示の出し方
- プロジェクトチーム編成におけるタスクフォース戦術の勧め
- 米海軍のイージス艦と海自イージス艦はどちらが強いか
- 民間企業の7不思議・・・ここを直せば組織が強くなる
- 薩摩の郷中教育と会津の什の掟/今こそ子供に必要な教え!
- 講演の申し込み

- 講演の申し込みははこちら
- セミナー実績
- ◆日本青年会議所近畿ブロックアカデミー委員会(約80名)に対する『率先垂範〜見せろ!リーダーの背中〜』(約5時間)
- ◆大手通信業界課長候補者(約50名)に対する班対抗、連帯責任方式によるリーダー集中セミナー 等々

- 詳細はこちら
- セミナーの問い合わせ
- ◆ご要望に応じたセミナーを企画・実施します。
- ◆お気軽にご相談下さい!
- セミナーの申し込みはこちらから
- 社員教育/研修について
- ◆新入社員教育
- ◆新入社員フォロー研修
- ◆管理職研修
- ◆リーダーシップ・フォロワーシップ研修
- ◆危機管理研修
- ◆詮議研修(郷中教育) 等々
- ◆ご要望に応じた社員教育・研修を企画・実施します。
- ◆お気軽にご相談下さい!
- 社員教育・研修の申し込みはこちらから
- お問い合わせ
- お問い合わせはこちらからお願いします。
- 問い合わせフォームで

◆世界最強! 海上自衛隊護衛艦のチーム力◆
私は海自においては護衛艦や護衛隊群、艦隊司令部の乗組み幹部、艦長、作戦幕僚等の勤務が約20年と恵まれた勤務であり、 毎年機会のある米国派遣訓練には8回参加、2年ごとに開催されるRIMPAC(Rim of the Pacific):環太平洋共同訓練には4回参加した。
米国派遣訓練や国内での米海軍との共同訓練はもとより、我が国に親善訪問した英・加・豪・仏・露・韓・チリ等の海軍と個別に親善訓練を行い、 また操艦技量や戦術技量を把握できる各種のイベントを行った経験を有しているが、
自信と確信を持って言えることは、海上自衛隊の部隊ほど一種独特の強くて柔軟性のあるチーム力を発揮できる海軍を見たことがありません。
海自のチームはまるで城壁の石垣のようであり、

石垣を構成する石であるチーム員は 石と石の間の隙間をチーム員がお互いに補完しながら見事に埋めて強固な石垣を形成してくれます。
欧米のチームの石垣の間を埋めて強固にするのはリーダーの役割です。
海自チームの石垣は指揮官の任務や目的に応じて柔軟に形も変えてくます。
海自現役時代、艦の能力は艦長の能力を超えることはない。と良く指導されました。
会社に言い換えれば、会社の能力は経営者の能力を超えることはない。ということです。
まさにその通りであり、石垣全体の広さは艦長や企業経営者の能力そのものであり、 海自や日本の社員のように人材が優秀で協調性を有する場合は、艦長や企業経営者の能力の広さに応じて、チーム員個々の石が大きく、 或いは小さくなり、隙間を見事に埋めてくれます。
このようなチームは、いかなる業務に対しても柔軟かつ完璧に応えてくれます。
これは日本人の価値観、精神文化による人間関係によって達成されるものす。
強くて柔軟なこの組織こそがグローバル化の将来に生き残る組織です。
○ 集団の力
人の成功、大成に最も影響を及ぼす要因は何でしょうか?
知識?
経験?
お金?
仲間?
あなたは何だと思いますか?
米国のハーバード大学の教授が約25年間にわたり調査したそうです。
人の成功、大成に最も影響を及ぼす要因、それは「集団(仲間)」だそうです。
私も海自の長い勤務を通じてその通りだと確信しています。
私は高校時代は鹿屋高校で柔道部に所属し、それなりの強さの2段でした。
しかし高校3年時の県大会で強豪校に1回戦で敗れました。
「はじめ」で組んだらまず畳の目を見よ、畳の目が見えたら落ち着いているので自信を持って技を掛けよ、 と祖父に柔道の試合に臨む心構えを指導されていました。
高校最後の県大会もその姿勢で臨みましたが、畳の目を見ようとしたら天井が見えました。
そうです、組んだら畳の目を見る暇もなくすぐに投げられていたのです。
私の高校は、大隅半島随一の進学校でしたが体育の部活も盛んな学校でした。
部員は15名程度でしたが、強い人は強く、弱い人は弱く、それなりの人はそれなりと言ったところで、 個人技量は徐々には向上していましたが、県大会で上位に勝ち進むような柔道部ではなかったように思っています。 (鹿屋高校柔道部の先輩、現役の皆様ごめんなさい。)
防衛大では少林寺拳法部でした。
防大の少林寺拳法部は昭和44年当時では同好会でしたが部員は100名を越えていました。
そして関東大会や全日本大会では常に優勝を競う強豪チームでした。
強いクラブに入り、仲間と同じように練習していると自然と強くなっていきました。
このように、私は普通の運動部と当時日本一の強い運動部を経験しました。
クラブの雰囲気がそのままチーム員の意識となります。
普通のチームには普通の意識、つまり全力を尽くせばそれで良しという意識があり、
強いチームには強い意識、つまり絶対に勝つ、絶対勝てるという意識があります。
普通の意識と強い意識はそのままチーム全員の意識となります。
その意思が練習にも表れて強いチームができている。
このように集団には「場の力」があります。
集団は時間の経過とともに同化し、
態度、行動、話し方、服装まで似てくるような印象を持っています。
そもそも、組織を作る目的は凡人に非凡なことをさせることです。
得意不得意を併せ持った人たちが、その得意な部分を出し合って一人では到底できないような偉大なことをする。
これが組織の強さです。